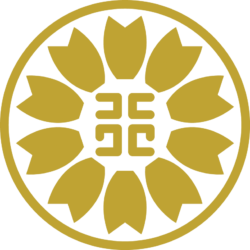法定相続分について解説
今回は「法定相続分」について解説します
法定相続分とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に、民法で定められた相続人の相続割合のことです。
相続人となるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが一般的で、それぞれの続柄によって相続割合が定められています。
なぜ「法定相続分」が必要なのか?
まず、遺言がない場合、法定相続分によって相続財産を公平に分割することを目的としています。
そして、法定相続分を基準とすることで、相続人間の争いを防ぐのです。
「法定相続分」の割合は相続人の構成によって異なります
配偶者しか血縁がいない場合は、配偶者が全財産を相続しますが、
配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が2分の1ずつ相続します。
配偶者と父母だけの場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を父母で相続します。
あとでその他の例も解説します。
法定相続分が適用されない場合はあるのか?
が気になりますね。遺言書で相続分が定められている場合は、法定相続分は適用されません。
代襲相続の場合は、例えば、子が死亡しており、孫が相続する場合、その孫は親の代わりに相続します。
また、特別受益で生前贈与など、生前に財産をもらった相続人は、その額を相続分から控除されることがあります。
法定相続分に関する注意点は?
相続分の注意点としては、遺留分があります。
一定の割合の財産は、他の相続人に相続させることができないという権利(遺留分)があります。
あとは、相続人の中に相続を放棄した人がいる場合は相続人が変わってきます。
法定相続分は、相続手続きにおいて非常に重要な概念です。
相続が発生した場合、必ず法定相続分を考慮する必要があります。
法定相続分は、相続人の構成によって大きく変わります。
法定相続分の代表的なケースとその割合
1.配偶者と子がいる場合
配偶者と、子が1人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1。配偶者と、子が2人いる場合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1づつ。
配偶者と、子が3人以上いる場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子供で等分。
2.配偶者と父母がいて、子はいない場合
配偶者と、父母が2人いる場合は、配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1で、各6分の1
3.配偶者と兄弟姉妹がいて、子はいない場合
配偶者と、兄弟姉妹が2人いる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1で、各8分の1
4.子だけいる場合
子が2人いる場合は、各子が2分の1づつ等分。
子が3人いる場合は、各子が3分の1づつ等分。となります。
法定相続分が複雑になるケース
相続人が多数いる場合は、相続人の数が多いほど、計算が複雑になります。
遺言がある場合は、遺言の内容によって、法定相続分が変更されることがあります。
生前贈与など、特別受益を受けた相続人がいる場合は、相続分が調整されます。
離婚して前妻の子がいる場合も相続人になります。
余談ですが、
両親が離婚してから何十年も父親と連絡をとっていない場合で、自分には子がおらず、兄弟しかいない場合は、自分が亡くなった時は、自分の兄弟が、何十年も会っていない父親に連絡を取らなければいけなくなるかもしれません。
子がいない方は予め遺言書を残しておくと良いでしょう。法定相続分は、あくまでも遺産分割の目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で、遺産を分割することも可能です。
また、相続人の中に認知症の方がいる場合も複雑です。
相続人が変わるわけではありませんが、スムーズに手続きができなくなるでしょう。
遺言書も無い場合は、認知症の方に負担をかけないよう、専門家に相談してください。
それから、これも余談ですが、
お金のように分割できるものは、この割合で相続すればいいのですが、
建物については、壊して分割することはできないですし、共有持分にすることはお勧めしません。
土地についても、1筆の土地を共有や分筆することも可能でしょうが、これもよく検討してください。
共有持分にしてしまうと、何十年後、何代かあとには、知らない人同士が、
その不動産を共有していることになっているかもしれません。
こうなると、相続手続きの際に、全く知らない人に事情を説明して、ハンコ代を持って、はんこをもらいに行くことになりかねないです。
なので、こういう場合は、遺産分割協議をして、誰かが代表で相続したほうが良いかもしれません。
また、古い農家さんは、農地を複数所有している方がいますが、どの地番にどれだけの土地と建物があるのか、きちんと把握できていない場合があります。
固定資産評価証明書や、名よせ帳、納税証明書、登記簿の内容を、一度よく整理しておくことをお勧めします。
もしかすると、過去に分筆や増築をしていて、現状と内容が合っていないかもしれません。
余談が長くなってしまいましたが、ここまで法定相続分について、いかがでしたでしょうか?
法定相続分は、相続人の構成によって大きく変わります。
ご自身の状況に合った相続分を、正確に把握するためには、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
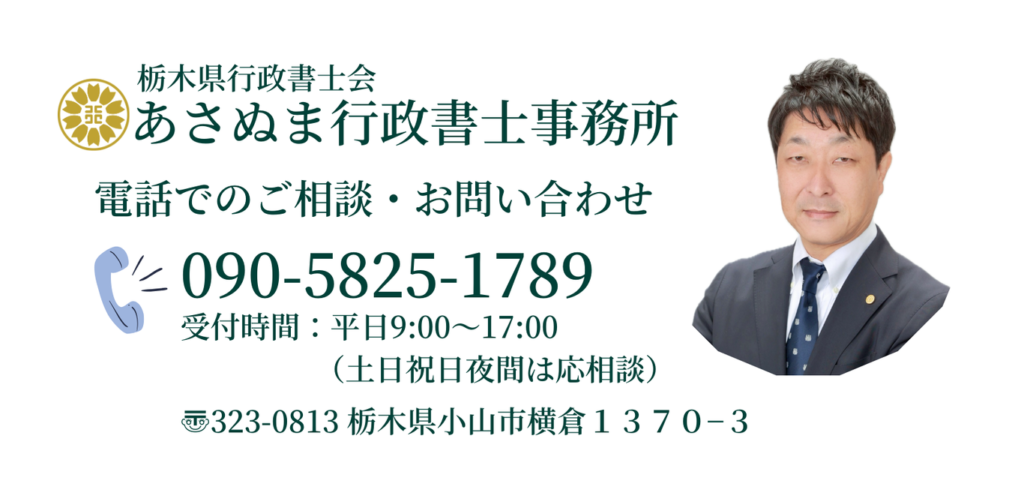
「あさぬま行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください。090-5825-1789受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日 夜間対応可 (要予約) ]
お問い合わせ